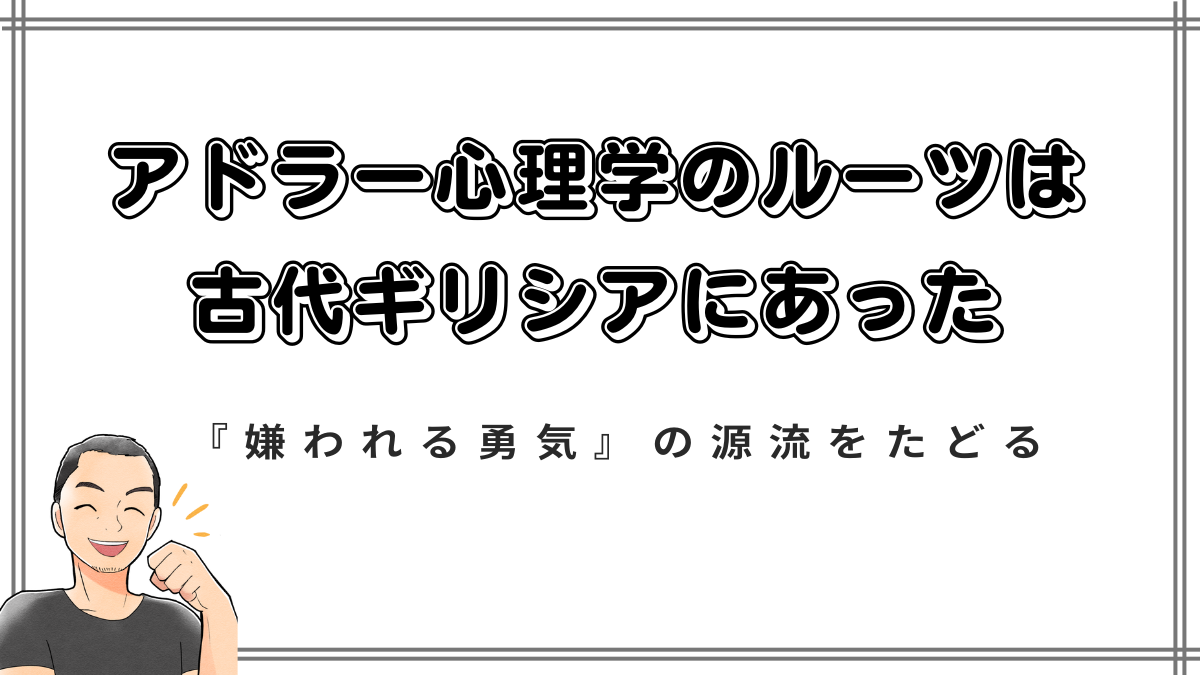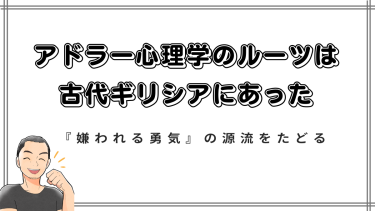人間関係の悩みから解放されたい…
もしあなたが今、こんな風に感じているなら、ぜひこの記事を読んでみてください。
ベストセラー『嫌われる勇気』で一躍有名になった「アドラー心理学」。
実はその思想の根っこをたどっていくと、なんと2000年以上も前の「古代ギリシア哲学」に行き着くことをご存知でしたか?
一見すると、心理学と哲学、全く別物のように思えますよね。
ところが、この二つには驚くほど多くの共通点があり、現代を生きる私たちの悩みを解決するヒントが隠されているのです。
この記事では、アドラー心理学とギリシア哲学の意外なつながりを解説していきます。
読み終わる頃には、あなたの世界観がガラッと変わり、もっと軽やかに生きるための「知恵」と「勇気」が手に入っているはずです。
アドラー心理学とギリシア哲学、驚きの共通点とは?

アルフレッド・アドラーは「すべての悩みは対人関係の悩みである」と断言しました。
一方で、古代ギリシアの哲学者たちもまた、「人間はいかに善く生きるべきか」を生涯かけて探求しました。
両者がたどり着いた答えには、不思議と重なる部分がたくさんあるのです。
共通点1:すべては「目的」のために(目的論)
アドラー心理学の根幹をなすのが「目的論」という考え方。
これは、人の行動は過去の「原因」によって決まるのではなく、未来の「目的」によって決まる、という視点です。
<人前で話すのが苦手なAさん>
- 原因論的な考え方:「過去に大勢の前で失敗して恥をかいたトラウマがあるから、人前で話せない」
- アドラー心理学の目的論:「『人前で話すことで、自分の未熟さがバレるのを避けたい』という目的のために、『緊張する』という感情や状況を作り出している」
つまり、話せないのではなく、「話さない」という目的を達成しているわけですね。
この考え方、実はギリシアの哲学者アリストテレスの思想とそっくり。
彼は、自然界のすべてのものには、そのもの本来の姿を実現するための究極的な「目的(テロス)」があると説きました。
例えば、ドングリの目的は樫の木になることです。
人間も同じように、「幸福になる」という目的を持っており、その目的のために行動している、と考えたのです。
過去の原因に縛られるのではなく、未来の目的に目を向ける。
この視点を持つだけで、なんだか前に進める気がしませんか?
共通点2:「共同体」の中でしか人は生きられない
アドラーは、人が幸福になるためには「共同体感覚」が不可欠だと考えました。
これは、他者を仲間だとみなし、そこに自分の居場所があると感じられる状態のこと。
そして、これもまたアリストテレスが人間を「ポリス的(社会的)動物」と呼んだことと深く関連します。
人間は一人では生きていけず、他者と関わる共同体(ポリス)の中でこそ、その本性を発揮し、幸福になれる存在である、と彼は見なしました。
SNSで孤立を感じたり、職場で疎外感を抱いたり…。
現代の私たちが抱える悩みの多くは、この「共同体感覚」の欠如からきているのかもしれません。
共通点3:対話を通じて「善く生きる」を探求する姿勢
「自分は何も知らない」という自覚から出発し、対話を通じて真理を探究した哲学者ソクラテス。
彼の姿勢は、アドラー心理学のカウンセリングにおけるクライエントとの関係性と非常によく似ています。
アドラー心理学のカウンセラーは、一方的に答えを与える(教育する)のではありません。
あくまで対等な立場でクライエントと対話し、本人が自らの力で気づきを得て、ライフスタイル(性格や価値観)を再選択するのを援助するのです。
- ソクラテスの問答法:対話によって相手の無知を自覚させ、真の知へと導く
- アドラー心理学の対話:対話によって本人の目的を明らかにし、勇気づけによって行動変容を促す
両者とも、答えは「外」から与えられるものではなく、自分自身の「内」にある対話を通して見つけ出すものだと考えていた点が興味深いですね。
なぜ今、この古代の知恵が必要なのか?

情報過多で、常に他者からの評価にさらされる現代。
私たちは、知らず知らずのうちに「他人のものさし」で生きようとして、疲弊してしまいがちです。
ここで役立つのが、アドラー心理学の「課題の分離」です。
これは、「自分の課題」と「他者の課題」を明確に線引きする考え方。
例えば、あなたが誰かに嫌われたとしても、それはあなたの課題ではありません。
「あなたをどう思うか」は、あくまでその他者の課題なのです。
この考えは、古代ギリシアのストア派の哲学者エピクテトスの教えにも通じます。
彼は「私たちを悩ませるのは物事そのものではなく、物事に対する私たちの意見である」と述べ、「私たち次第であること(自分の解釈や行動)」と「私たち次第でないこと(他人の評価や運命)」を区別せよ、と説きました。
SNSの「いいね」の数に一喜一憂したり、他人の機嫌に振り回されたり…。
そんな時は一度立ち止まって、「これは、果たして自分の課題だろうか?」と問いかけてみましょう。
それだけで、心がスッと軽くなるのを感じられるはずです。
明日から実践!ギリシア哲学に学ぶアドラー的生き方のヒント
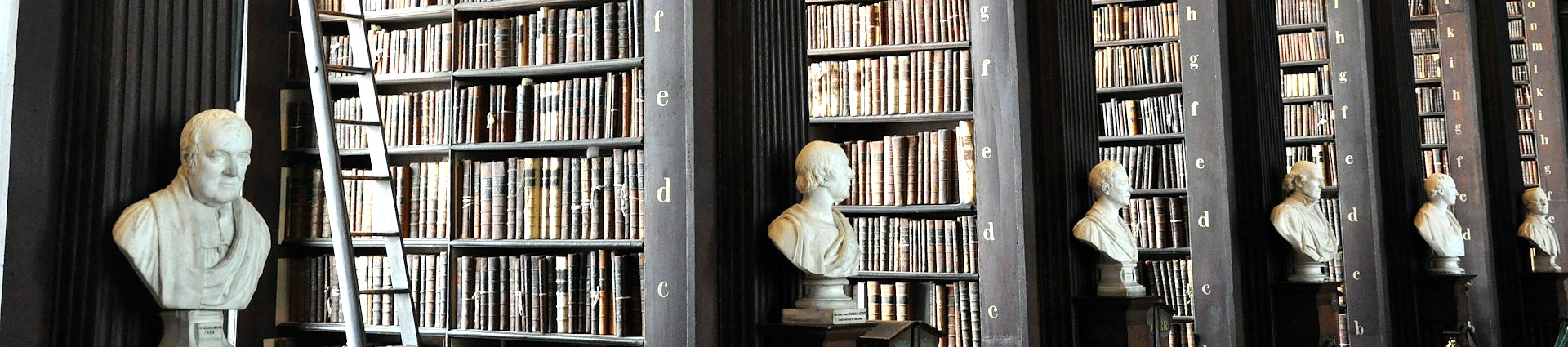
知識として知っているだけではもったいない!今日からあなたの日常に取り入れられる、具体的なアクションプランを3つご紹介します。
① ソクラテスのように「自分に問いかける」
「なぜ私はイライラしているんだろう?」
「この行動の本当の目的は何?」と、
自分の感情や行動の裏にある「目的」を自問自答するクセをつけてみましょう。
自分の心の声に耳を澄ます、良いトレーニングになります。
② アリストテレスのように「中庸」を意識する
対人関係において、言いたいことを我慢しすぎる(臆病)のでもなく、相手を攻撃する(無謀)のでもなく、その中間である「適切な自己主張(アサーティブネス)」を心がけてみてください。
「私はこう思う」「私はこうしてほしい」と、主語を「私」にして伝えるのがポイントです。
③ エピクテトスのように「変えられること」に集中する
天気や過去、そして他人の気持ちなど、自分ではコントロールできないことで悩むのはやめましょう。
変えられるのは、いつだって「自分の解釈」と「これからの行動」だけ。
その事実に集中すれば、無駄なエネルギーを使わずに済みます。
もっと深く知りたいあなたへ【おすすめの書籍】
今回の話でアドラー心理学やギリシア哲学に興味が湧いた方は、ぜひ以下の本を手に取ってみてください。
きっと、あなたの人生を豊かにする、新たな発見がありますよ。
【アドラー心理学入門の決定版!】
- 『嫌われる勇気』『幸せになる勇気』岸見一郎・古賀史健 言わずと知れた名著。哲人と青年の対話形式で、アドラー心理学のエッセンスが驚くほど分かりやすく解説されています。まだ読んでいない方は、まずはこちらから!
【ギリシア哲学の世界へようこそ!】
- 『ソクラテスの弁明・クリトン』プラトン 2000年以上も読み継がれる古典中の古典。哲学の原点に触れ、「善く生きるとは何か」を深く考えさせられます。
知識を得て、「なるほど!」で終わらせるのは非常にもったいないことです。
もし、一人で実践するのが難しい、自分の課題を整理したいと感じたら、専門家の力を借りるのも賢い選択肢。
オンラインカウンセリングなどで、プロと対話してみるのもおすすめです。
まとめ
アドラー心理学とギリシア哲学。この二つは、時代や場所を超えて、「いかに幸福に生きるか」という私たち人間の普遍的な問いに、力強い答えを与えてくれます。
- 過去の原因ではなく、未来の目的に目を向ける(目的論)
- 他者と協力し、共同体の中に居場所を見出す(共同体感覚)
- 自分の課題と他者の課題を切り分け、変えられることに集中する(課題の分離)
これらの知恵は、決して難しいものではありません。
むしろ、非常にシンプルで、力強いものばかり。
古代の賢人たちの声に耳を傾け、アドラーの「勇気」を手にすることで、あなたの日常はもっとシンプルで、幸福なものに変わっていくはずです。